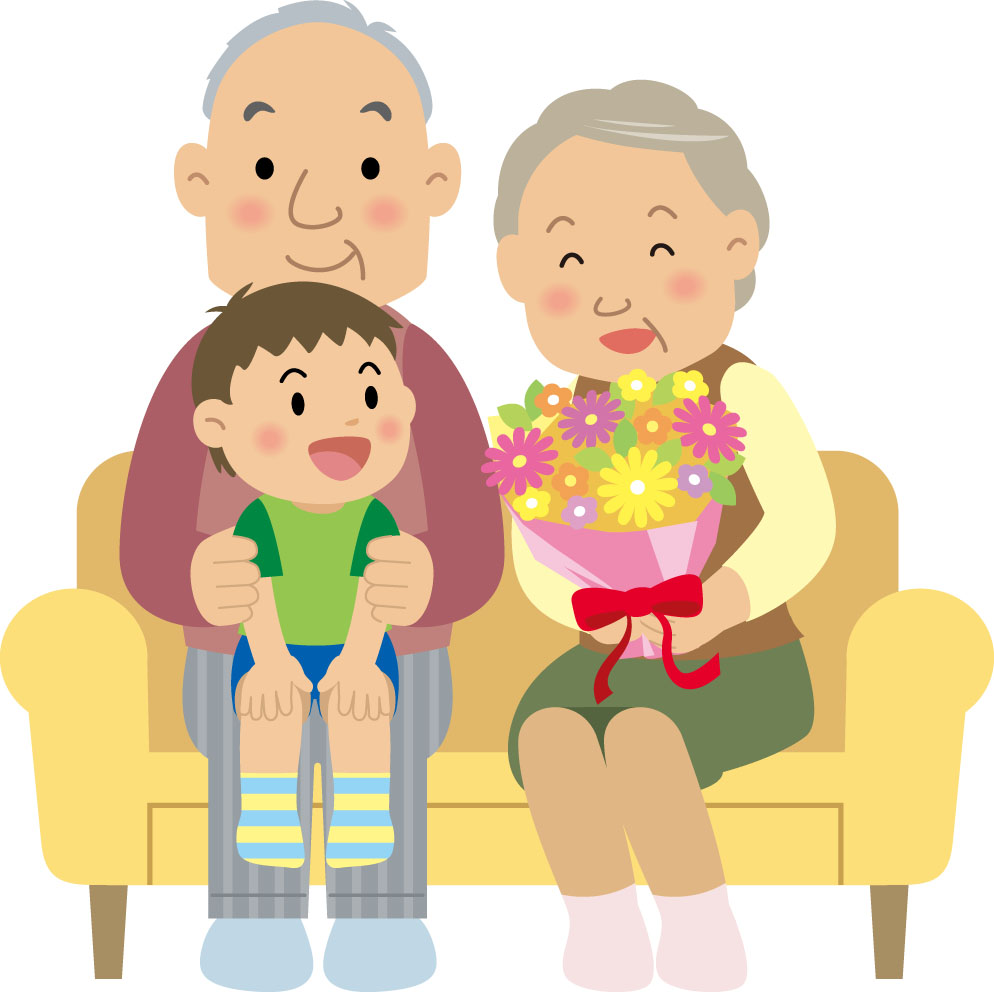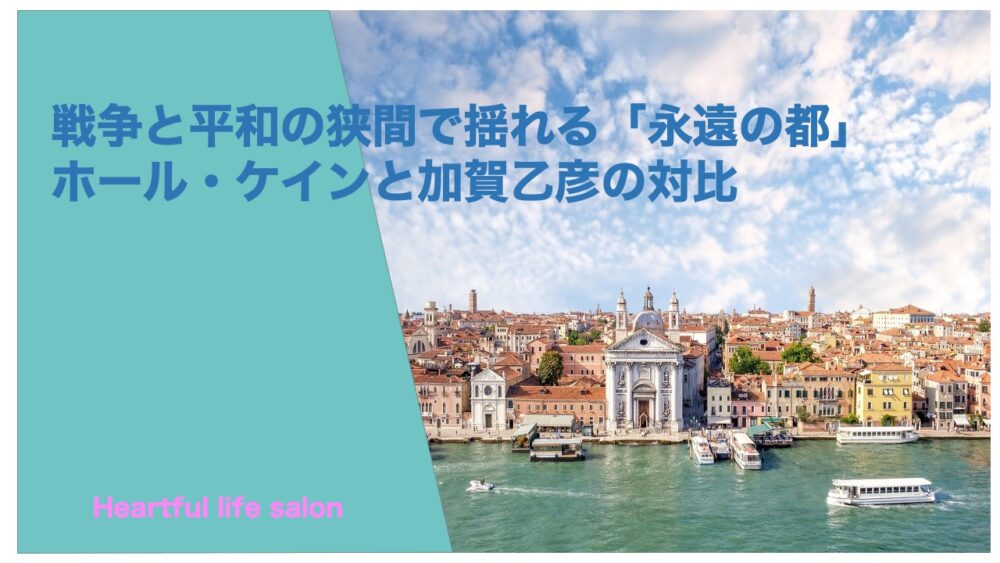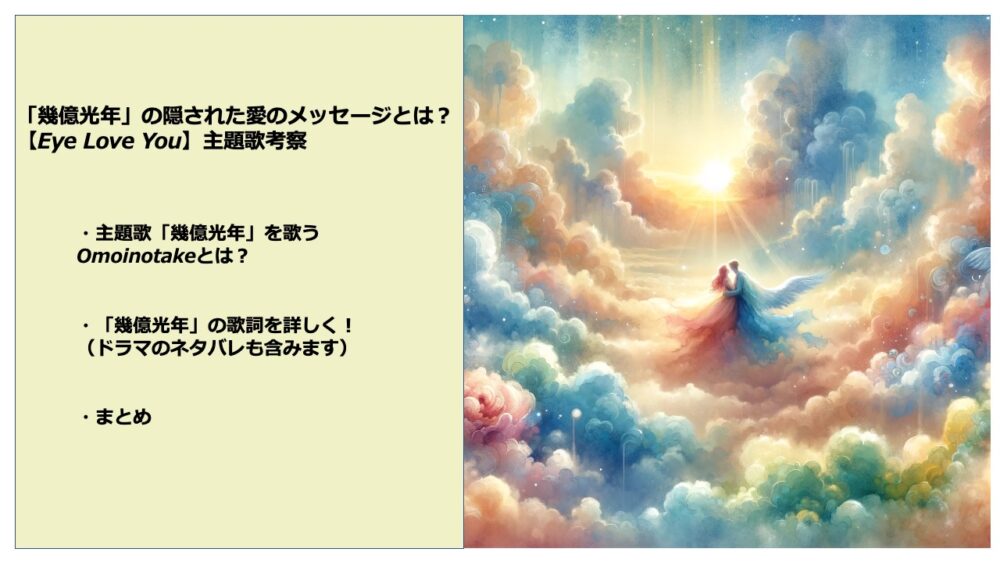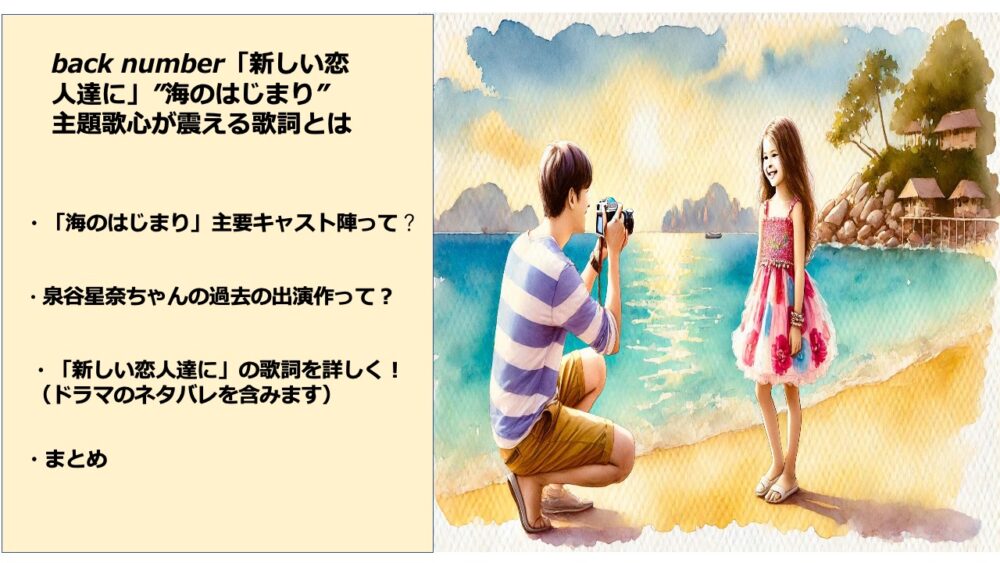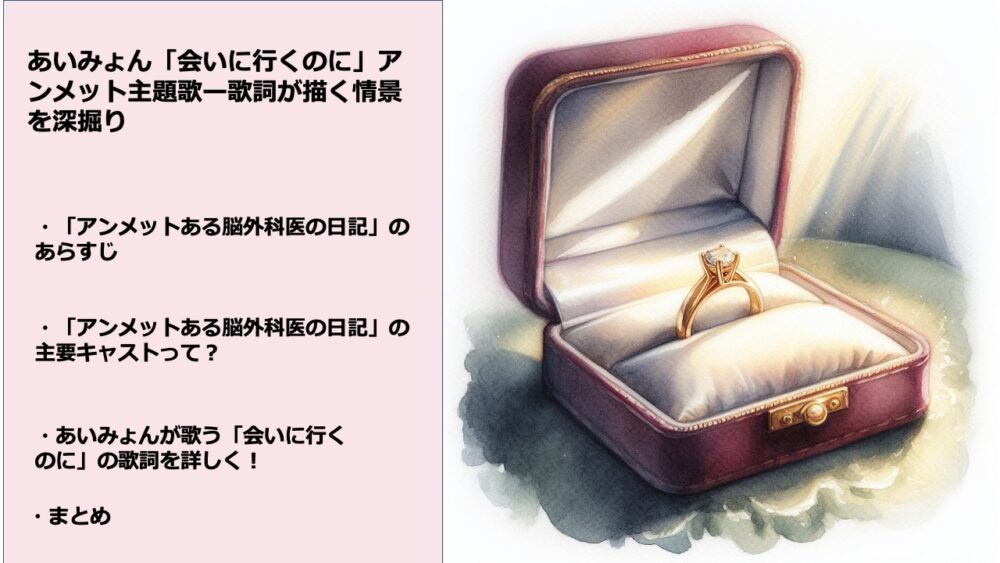「心に残るおすすめの本はありますか?」ってもし聞かれたら、
たくさんありすぎて困ってしまいますが、その中の一つを挙げるとしたら、
「永遠の都」(ホール・ケイン著)と答えると思います。
ホール・ケイン氏はイギリスの小説家ですが、日本では、加賀乙彦さんが書かれた同じ題名の「永遠の都」がありますので、今回それぞれの著者の人物像や書籍の内容を比べてまとめてみました。何かの参考になれば嬉しいです。
加賀乙彦さんってどんな人なの?
加賀乙彦さんは、日本の小説家であり、医学者(犯罪心理学)や精神科医でもありました。 1929年に東京に生まれ、東京大学医学部を卒業しました。 フランスに留学した後、1967年に『フランドルの冬』で小説家としてデビューしました。 その後、『帰らざる夏』や『宣告』など、多くの長編小説を書きました。 加賀さんの小説は、精神医学や犯罪心理学の知識を活かして、人間の生と死の問題に深く切り込んだ作品が多く、数々の賞を受賞しました。
1998年には「永遠の都」が 芸術選奨文部大臣賞を受賞されました。残念ながら、今年2023年1月に93歳で亡くなりました。ご冥福をお祈りします。
日本の「永遠の都」はどんな内容なの?
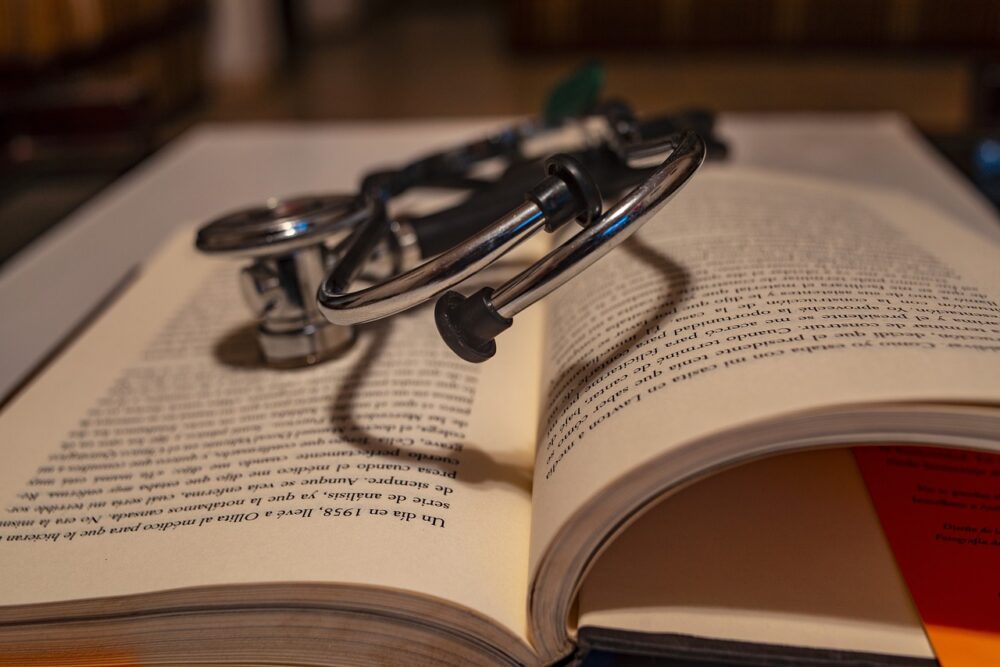
「永遠の都」は、加賀乙彦さんが1986年から1995年にかけて書いた自伝的な大河小説です。この小説は、昭和10年から22年までの日本を舞台に、戦争の時代に生きる大病院長の一族を描いています。
主人公は、時田利平という元海軍軍医で、貧しい家から身を起こして東京三田に大外科病院を作り上げた人物です。彼は医学研究や発明に情熱を注ぎ、多くの患者や同僚の尊敬を集めます。しかし、彼は家族や恋人との関係に苦悩し、戦争や政治の動きにも巻き込まれていきます。
時田利平は、次々と試練に直面します。例えば、
・長女の初江が一高生の甥と不倫し、妊娠する。
・次女の夏江が陸軍中尉・脇敬助と恋に落ちるが、敬助が二・二六事件に関与し、逮捕される。
・長男の晋助が文学と音楽に傾倒するが、出征して戦場で自殺する。
・次男の悠太が医師となるが、戦争で負傷し、左手を失う。
・三男の俊太が空襲で死亡する。
・妻の菊江が癌で余命宣告される。
・病院が空襲で焼失する。
・戦後、敗戦責任を問われて逮捕される。
などです。
あまりにも壮絶すぎる内容ですね。
この本は、戦争の時代に何があったかを検証し、その中で生きる人々の喜びや悲しみや絶望を伝えようとしているように思います。また、家族や恋人との絆や信頼、医学や芸術への情熱や探求心など、人間の持つ普遍的な価値や魅力も描いていますので奥が深くて読み応えのある小説です。
主人公、時田利平が残した言葉には次のようなものがあります。
「私はこの国が好きだった。 この国が私に与えてくれたものは何もない。 それでも私はこの国が好きだった」(第一巻)
出典元:「永遠の都」第1巻(加賀乙彦著)
どうしてこんな言葉を時田は言ったのでしょうか?
この言葉は、時田利平が中国に対して抱いていた複雑な感情を表していると思います。時田利平は、日中戦争の勃発によって、日本と中国の間で選択を迫られます。彼は日本人として生まれましたが、中国で育ち、中国の文化や人々に親しみを感じていました。しかし、中国は彼にとって敵国であり、彼は日本の外交官として中国に対する任務を負っていました。彼は中国に対して愛情や尊敬を持っていましたが、同時に中国から苦しみや裏切りを受けていました。彼は中国が自分に与えてくれたものは何もないと言いますが、それでも中国が好きだったと言います。これは、彼が中国に対して理性ではなく感情で結びついていたからこそ、上記のような言葉が出てきたのかなと思います。
「私は愛することを知らなかった。 愛することがどんなに大切なことかわからなかった。 愛することがどんなに幸せなことかわからなかった」(第六巻)
出典元:「永遠の都」第6巻(加賀乙彦著)
この文章は、主人公の時田利平が自分の恋人である葉子に対して語った言葉です。
時田利平は、戦争の時代に生きる医師として、多くの患者や同僚の尊敬を集めましたが、家族や恋人との関係に苦悩しました。彼は葉子と結婚することを望んでいましたが、葉子は彼の子供を身ごもった後に別の男と結婚しました。(辛いですね)
彼はそのことを知っても、葉子を愛し続けましたが、自分の気持ちを伝えることができませんでした。もし伝えていたら人生が変わっていたのかもしれないですね。
この文章は、彼が葉子に対して抱いていた後悔と悲しみを表しています。彼は愛することの大切さや幸せさを知らなかったと言っていますが、本意じゃないかもしれないです。それは自分が愛することに恐れていたからなのではと思います。彼は愛することによって傷つくことや失うことを避けようとしていましたが、それがかえって自分を苦しめることになりました。 この文章から、愛することの難しさや切なさが伝わってきますね。
自分が傷つくことを避けようとしたのに、結局そのことが自分に降りかかってきて苦しむことって、日常生活でもあります。人は誰でも、心が傷つきたくないですものね。
相手に見返りを求めない「無性の愛」って言葉がありますが、自分のことより相手のことを思って行動することなので、相手のためになるなら自分の心が傷ついてもいいってことになるのでしょうか?
本当、愛するってことは難しいですね。
でも、本当の愛はもしかしたらシンプルなのかもしれないです。利害関係がなく、純粋にストレートに愛することができたら一番幸せかなと思います。
関連記事↓

イタリアが舞台になった「永遠の都」とは?

ホール・ケインの小説「永遠の都」は、1901年に出版され、イギリスとアメリカで大ヒットしました。この小説は、19世紀末のイタリアを舞台にしており、当時の国は政治的・社会的な混乱に見舞われていました。この小説の主なテーマは、人間の尊厳と平等に基づく人間共和国を求める闘争であり、それは王制や教会の圧政に対抗するものでした。
ホール・ケインってどんな人なの?
1853年から1931年まで生きたホールケインは、1853年から1931年にかけて活躍したイギリスの小説家で、マン島出身のアイルランド人でした。彼は、幼い頃から文学に興味を持ち、ダブリン大学で学びました。彼は、有名な俳優ヘンリー・アーヴィングのマネージャーとして働きながら、小説や劇評を書きました。
彼は、画家ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティと親友であり、彼の影響を受けた作品も多くあります。彼の代表作は、『永遠の都』や『キリストの子』などで、イタリアや聖書を題材にした歴史小説や社会小説が多くあります。彼は、当時のイギリスで最も人気のある作家の一人でしたが、現在ではあまり知られていません。彼は、情熱的で冒険好きな人物でしたが、同時に宗教的で保守的な人物でもありました。彼はまた、ジャーナリストや劇作家としても活動し、ブラム・ストーカーという文学者とも交流しました。
ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティとは、19世紀のイギリスの画家で詩人です。ラファエル前派という芸術運動の一員で、自然や文学に題材をとった作品を多く描きました。彼はまた、詩集『生命の家』や『ジェニー』などの詩作も残しています。彼の絵画や詩は、ロマンチックで神秘的な情感を表現しており、装飾的で耽美的な画風が特徴です。彼は、妻であったエリザベス・シダルや、友人の妻であったジェーン・モリスという二人の女性との関係にも影響を受けました。彼の代表作には、『受胎告知』、『プロセルピナ』、『ベアタ・ベアトリクス』などがあります。
ブラム・ストーカーとは、イギリス時代のアイルランド人の小説家で、怪奇小説の古典『ドラキュラ』の作者です。彼は、病弱な幼少期を経て、ダブリン大学で学び、劇評や小説を書き始めました。彼は、有名な俳優ヘンリー・アーヴィングのマネージャーとして働きながら、文学界とも交流しました。彼は、ルーマニアの歴史や伝説に触発されて『ドラキュラ』を執筆しましたが、その作品は彼の死後に映画化されて広く知られるようになりました。彼は、他にも『日没の下』や『男』などの作品を残しましたが、『ドラキュラ』ほどの成功は得られませんでした。彼は、情熱的で創造的な人物でしたが、同時に忠実で勤勉な人物でもありました。
ホール・ケインの「永遠の都」の内容とは?
彼が書いた『永遠の都』は、1901年に出版され、イギリスとアメリカで大ヒットしました。この頃のイタリアは1870年にローマを首都として統一されましたが、教皇領として独立していたバチカンとの関係は悪化しました。また、社会主義や無政府主義の運動が盛んになり、暗殺や暴動が頻発が多くあり社会が乱れていました。
この小説の主なテーマは、人間の尊厳と平等に基づく人間共和国を求める闘争であり、それは王制や教会の圧政に対抗するものでした。また、当時のイタリアの歴史や文化を豊富に取り入れており、実在の人物や事件も登場します。
例えば、ジュゼッペ・マッツィーニやジュゼッペ・ガリバルディなどの統一運動の指導者や、バンバ事件などの政治的暗殺事件が描かれています。
主人公のロッシの人物像とは?
この小説の主人公は、デイビッド・ロッシという若いジャーナリストで政治家で、非暴力革命を唱えていました。彼は孤児で、小さな村で老学者に育てられました。彼はドンナ・ローマという美しくて裕福な女性と恋に落ちますが、彼女は幼なじみであることが判明します。彼女はまた、首相でありロッシの宿敵であるバロン・ボネッリの姪でもありました。
ロッシは、人間共和国を目指して多くの困難や危険に直面します。彼は殺人の罪で告発されたり、友人に裏切られたり、警察に追われたり、イギリスに亡命したりします。彼はまた、子供を失ったり、ローマと離れたりする苦しみにも耐えます。彼は常に、ローマへの愛と自分の信念への忠誠との間で引き裂かれます。
読み進めていくうちに、「永遠の都」の世界観に引き込まれて、私自身も同じように苦しくなったり誰を信じていいのかわからないような気持ちになったことを覚えています。
ローマもまた、わがままで自分勝手な貴族から高潔で犠牲的なヒロインへと変貌を遂げます。彼女は自分の富や権力を捨ててロッシの理想に加わtたり、自分の利益のために彼女を操ろうとする叔父に反抗したりします。彼女は強い心で、愛と信仰のために貧困や屈辱や迫害に耐えていきます。とても真似できることではないですが、少しでも見習いたいと思います。
この小説は、古いものと新しいもの、金持ちと貧乏人、圧制者と被圧制者との衝突を描いたスリリングでロマンチックな冒険物語です。また、友情や裏切りや犠牲や贖罪や運命などのテーマも探求しています。この小説は、読者に自分の夢を追い求めることや自分の権利を戦うことを奨励することを目指しています。それは逆境に直面してもです。また、暴力や腐敗よりも愛や人間性の力を讃えている内容となっています。
なんと言っても、クライマックスには驚きが隠せませんでした。途中、読むのが辛くなる時があるのですが、読まれる際には、クライマックスまでたどり着いて欲しいです!ぜひ、ぜひ・・・
心に残った主人公ロッシの言葉とは?
気高き志を持ったロッシが残した言葉はたくさんあります。
その中から少し紹介しますね。
「私は詩人だ。私は美しさを見ることができる。私は美しさを感じることができる。私は美しさを言葉にすることができる。しかし私は美しさを作り出すことができない」
引用元:「永遠の都」(ホール・ケイン著)
これは、ロッシが彫刻家のローマに恋したときに言った言葉です。彼は、彼女の才能と美しさに惹かれましたが、自分の不器用さや不幸さに苦しみました。
どうしてロッシが苦しんでいたのかなと考えてみたのですが、ロッシは詩人としての自分の能力に誇りを持っていましたが、同時に自分の限界にも気づいていました。
また彼は、自分の言葉で美しさを表現することができましたが、自分の手で美しさを形作ることができない上に、自分にはそのような技術や才能がないことに劣等感を感じていたと思います。
彼は、勇気を出してローマに愛を告白しましたが、自分には彼女を幸せにすることができないことに不安を抱いていました。本当、不安はつきものですよね。
主人公ロッシとローマは結ばれるのかどうかが気になるところですが、それは読んでからのお楽しみということで・・・
まとめ
同じ題名の本を書かれた二人の作家、ホール・ケインと加賀乙彦氏。
ホール・ケインは、1853年5月14日にマン島で生まれ、1931年8月31日にロンドンで亡くなりました。
一方、加賀乙彦さんは、1929年4月22日に東京で生まれ、2023年1月12日に老衰のため亡くなりました。
お二人が生きていた時代は違いますが、「永遠の都」が書かれた時代背景には必ず平和と戦争で揺れ動く人々の葛藤があり、現在より生きにくい時代だったのかなと思います。
そう考えると、今の時代を生きてるだけで幸せなんだなあって感じます。いろいろ理不尽だったり辛いことがあったりしますが、平和を絶対手放さないようにしたいです。
最後までお読みいただきありがとうございました!