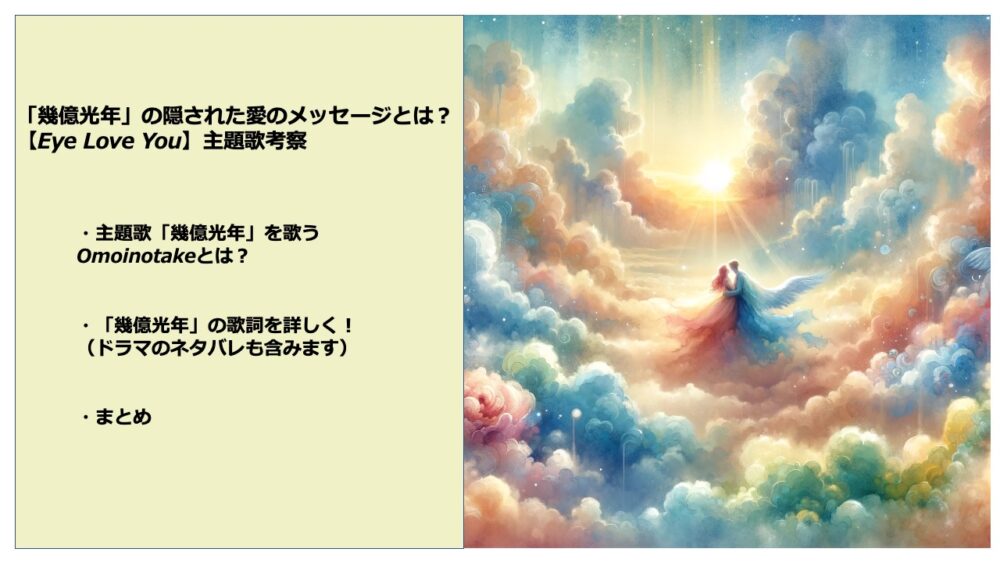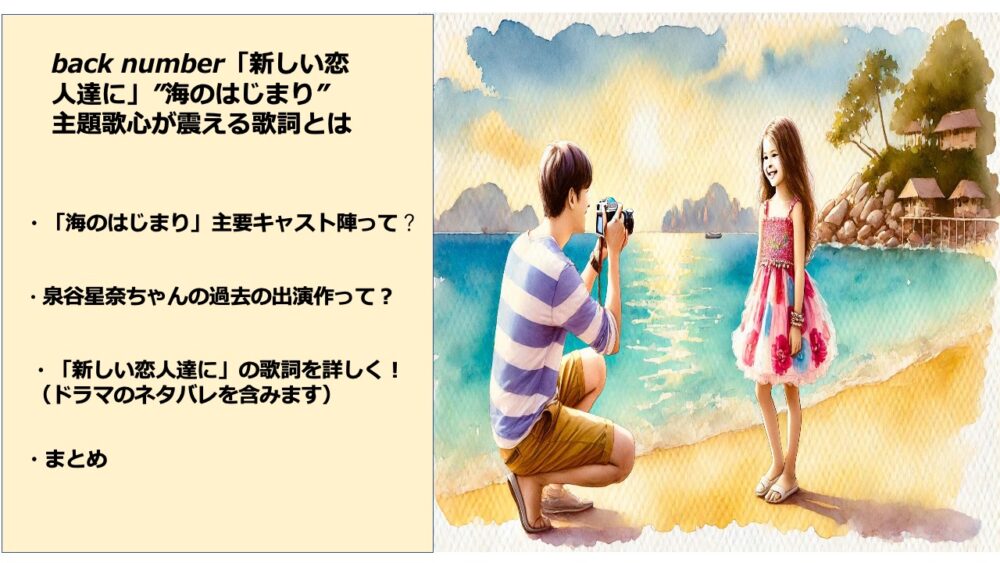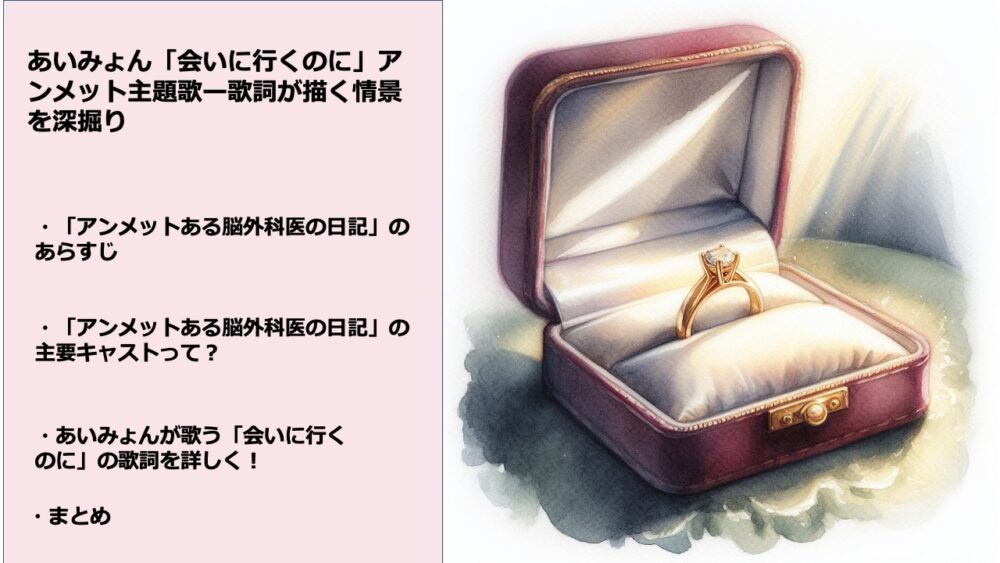森の中でひっそりと、生き続けているキノコ。その神秘的な存在は、多くの人々を魅了してやみません。
前回のブログでは「キノコの不思議な世界」について様々まとめてみましたが、今回この記事では、キノコの誕生から栽培方法、初心者におすすめの種類までをご紹介します。
キノコの誕生

もし、キノコの女神様がいたら、こんなイメージかな?
あくまでもメルメンの世界の中だけですが(笑)
キノコは、菌類の一種であり、その多くは「担子菌類」と「子のう菌類」に分類されます。これらの菌類は、約2億年前の白亜紀時代に地球上に出現しました。
キノコが形成される過程は、自然界の中で複雑な相互作用を経て行われます。まず、菌類は、植物や動物の死骸などの有機物を分解することで、栄養を得ます。このとき、菌類は、細い糸状の菌糸と呼ばれるものを伸ばして、有機物の内部に侵入します。菌糸は、菌類の本体であり、目に見えないほど小さいです。
キノコが生まれる仕組みは、植物や動物とは異なります。
それにキノコは、花や種子をつけることはありません。
本当に不思議な生物ですよね。
キノコは、有機物の中で成長し、他の菌糸と交配することで、遺伝子を混ぜ合わせます。このとき、菌糸は、環境に応じて、さまざまな形や色のキノコを作り出すことができます。キノコは、菌類の生殖器官であり、菌糸から出芽するようにして現れます。キノコは、胞子と呼ばれる微細な粒子を放出することで、新たな菌類の個体を生み出します。胞子は、風や水や動物によって運ばれて、有機物の上に落ちると、菌糸を発生させます。このようにして、キノコは、自然界の中で繁殖していきます。
こうやって広まった自然界にあるキノコ全てが、私たち人間にとって有益なキノコばかりではないです。
それでも知恵ある大昔の人達は、食用のキノコを栽培することを思いつきました。
すごいですね!
では、どうやってきのこを栽培していくのでしょう?
次の章で、まとめたいと思います。
キノコの栽培の基礎知識とは?
キノコ栽培とは、人工的にキノコに適した環境を作って、キノコを育てることです。キノコ栽培には、以下のようなメリットがあります。
- ビタミンやミネラルなどの栄養素が豊富で、健康に良い食材です。
- さまざまな料理に使えるので、食卓のバリエーションが増えます。
- 自然に発生するものよりも安全で衛生的です。
- 季節や天候に左右されずに収穫できるので、安定した収入源になります。
キノコ栽培とは、キノコの菌を人工的に増やして、食用や観賞用に収穫することです。キノコは、菌類の一種であり、その多くは「担子菌類」と「子のう菌類」に分類されます。これらの菌類は、約2億年前の白亜紀時代に地球上に出現しました。
関連記事

キノコ栽培には、
原木栽培と菌床栽培の2つの主要な方法
原木栽培は自然に近い環境で行われ、菌床栽培は室内で温度や湿度を管理しながら行います。栽培に成功するためには、適切な知識と技術が必要です。
またクヌギやナラなどの原木に種駒(たねこま/キノコの菌をつけた木片)を埋め込んで栽培するもので、主にシイタケ、ナメコに用いられます。原木栽培の流れは、以下の5ステップに分けられます。
原木栽培
原木の準備:原木は、冬に伐採したものが適しています。直径は10~15cm、長さは1m程度に切ります。原木には、菌が入りやすいように、5cm間隔で直径1cmほどの穴をあけます。
種駒の植え付け:穴に種駒を入れて、ワックスで封じます。種駒は、市販のものを使うか、自分で作ることができます。自分で作る場合は、木片にキノコの菌を植え付けて、温度と湿度を管理して培養します。
原木の保管:植え付けた原木は、日陰で風通しの良い場所に立てかけて保管します。保管期間は、キノコの種類によって異なりますが、一般的には半年から1年程度です。この間に、菌が原木の中に広がります。
原木の露地出し:保管期間が終わったら、原木を露地に出します。露地は、日陰で水はけの良い場所にします。原木は、水を吸わせるために、水槽や川などに浸します。浸す時間は、キノコの種類によって異なりますが、一般的には1~2週間程度です。
キノコの収穫:露地に出した原木から、キノコが出始めます。キノコは、傘が開く前に収穫します。収穫後は、原木を再び水に浸して、次の発生を促します。原木は、キノコが出なくなるまで、何度も収穫できます。
菌床栽培は、おがくずに穀物の粉などを混ぜたブロック状の菌床にキノコの菌を植えつけ、室内で温度や湿度を管理して栽培するもので、主にエノキタケ、マイタケ、エリンギなどに用いられます。菌床栽培の流れは、以下の4ステップに分けられます。
菌床栽培
菌床の準備:菌床は、市販のものを使うか、自分で作ることができます。自分で作る場合は、おがくずに穀物の粉や石灰などを混ぜて、高温で殺菌します。殺菌後は、菌床を冷まして、袋に詰めます。
菌の植え付け:菌床にキノコの菌を植え付けます。菌は、市販のものを使うか、自分で作ることができます。自分で作る場合は、穀物や木片にキノコの菌を植え付けて、温度と湿度を管理して培養します。
菌の培養:植え付けた菌床を、暗くて温度の安定した場所に置いて、菌の培養を行います。培養期間は、キノコの種類によって異なりますが、一般的には1~2ヶ月程度です。この間に、菌が菌床の中に広がります。
キノコの収穫:培養期間が終わったら、菌床の袋に穴をあけて、キノコが出るのを待ちます。キノコは、傘が開く前に収穫します。収穫後は、菌床の袋を再び閉じて、次の発生を促します。菌床は、キノコが出なくなるまで、何度も収穫できます。
以上が、キノコ栽培の基礎知識です。
キノコ栽培は、低カロリーで栄養豊富な食材を自分で作れるだけでなく、キノコの成長を観察する楽しみもあります。初心者には、見分けやすく、採りやすいキノコがおすすめです。アミタケ、アカヤマドリ、サラダタケなどが挙げられます。市販のキノコ栽培キットを使えば、手軽にキノコ栽培を始めることができます。
キノコ栽培に興味がある方は、ぜひチャレンジしてみてください。キノコの魅力にハマること間違いなしです!
キノコ栽培におすすめの種類とは?
- エリンギ:白くて長い柄が特徴的なキノコです。肉厚で歯ごたえがあり、炒め物やスープなどに向いています。栽培方法は比較的簡単で、菌床と呼ばれる培地に穴を開けて菌糸を入れておくだけです。
- ブナシメジ:茶色い帽子が可愛らしいキノコです。香りが良くて風味豊かで、サラダやパスタなどに向いています。栽培方法はエリンギと同じですが、温度管理が重要です。15℃~20℃が最適です。
- マイタケ:ひだ状に重なった帽子が特徴的なキノコです。ほくほくとした食感で、煮物や天ぷらなどに向いています。栽培方法は、木の切り株や丸太に菌糸を打ち込んでおくだけです。ただし、発生までに半年から1年ほどかかります。
食用キノコの種類と特徴とは?

私たちの食事に欠かせないキノコですが、この章ではどんなキノコの種類があるのかみていきますね。
※キノコのキャラクターは架空のオリジナルです。
シイタケ:広葉樹の原木や菌床で栽培される。肉厚で旨味が強く、乾燥させると香りが増す。食物繊維やカリウム、ビタミンDなどが豊富。

(しいたけのシーくんです)
マッシュルーム:ヨーロッパ原産で、菌床で栽培される。白い傘と柄が特徴で、味や香りがあっさりしている。ビタミンB群やナイアシンなどが含まれる。

(マッシュルームのマー君です)
エノキタケ:広葉樹の原木や菌床で栽培される。細長い柄と小さな傘が特徴で、シャキシャキとした食感が楽しめる。リラックス効果があるとされるギャバが豊富。

(えのきだけのエキちゃん)
マイタケ:広葉樹の根元に自生するが、菌床で栽培されることも多い。重なり合った葉状の部分が特徴で、弾力があってコリコリとした食感がある。プロアテーゼというタンパク質分解酵素が含まれる。

(まいたけのマーリンちゃん)
エリンギ:ヨーロッパ原産で、菌床で栽培される。太い柄と平たい傘が特徴で、コリコリとした食感がアワビに似ている。食物繊維が豊富。

(エリンギのエギ紳士)
ヒラタケ:広葉樹の倒木などに自生するが、菌床で栽培されることも多い。平たい傘と短い柄が特徴で、香りが良くて歯応えがある。葉酸やカリウムなどが含まれる。

(ヒラタケのヒーちゃん)
ブナシメジ:広葉樹の倒木に自生するが、菌床で栽培されることも多い。癖のない味わいが特徴で、栽培したものは年間を通して食べられる。食物繊維やカリウム、ビタミンDなどが含まれる。

(ブナシメジのメジちゃん)
ナメコ:広葉樹の倒木や切り株などに自生するが、菌床で栽培されることも多い。ぬめりが特徴で、煮るととろみが出る。食物繊維やカリウムなどが含まれる。

(ナメコのナーちゃん)
キクラゲ:広葉樹の枯れ木などに自生するが、菌床で栽培されることも多い。黒くて薄い皮状の部分が特徴で、コリコリとした食感がある。食物繊維やビタミンDなどが含まれる。

(キクラゲのキーくん)
マツタケ:松の根に共生するが、人工栽培方法が未確立。芳醇な香りが特徴で、高級キノコとされる。食物繊維やカリウム、ビタミンDなどが含まれる。

(マツタケのマーケさま)
以上が、日本でよく食べられている食用キノコの種類でしたが、いかがだったでしょうか?
好きなキノコはありましたか?
キノコがもっと好きになれるように、キャラクターを考えてみました(笑)
私が好きなのは、(どの子も好きですが)マッシュルームのマー君とエノキダケのエキちゃんです。
このキノコのキャラクターたちでお話が作れそうですが、私には才能がないので観るだけにしますね(笑)
「誰かに話したくなるキノコの不思議な世界」の本はこちら
まとめ
食用キノコは、低カロリーで栄養豊富な食材ですが、毒キノコと間違えて食べないように注意してくださいね。
毒キノコは、色や形が食用キノコに似ていることがありますが、熱に弱いものは少なく、加熱しても毒性が変わらないことが多いから、本当に気をつけないといけないですね。
自然界に生えているキノコを採る場合は、専門家に確認するか、きのこ図鑑などを参考にして、食べられるものかどうかをしっかり判断することが大事です。
今回、キノコの誕生についてやキノコの種類などについてまとめました。
キノコの種類の説明のところで、キノコのキャラクターがあったら楽しくて親しみやすいかなと思い、脱線してしまいました。すみません。
これからも栄養があって体にいいキノコを食べたいなって思います。
最後までご覧いただきありがとうございました!