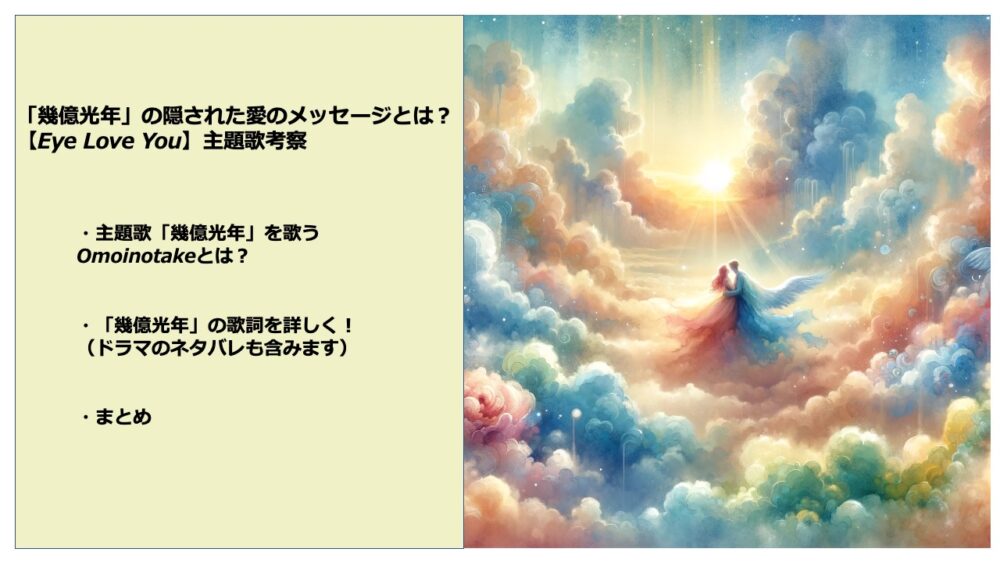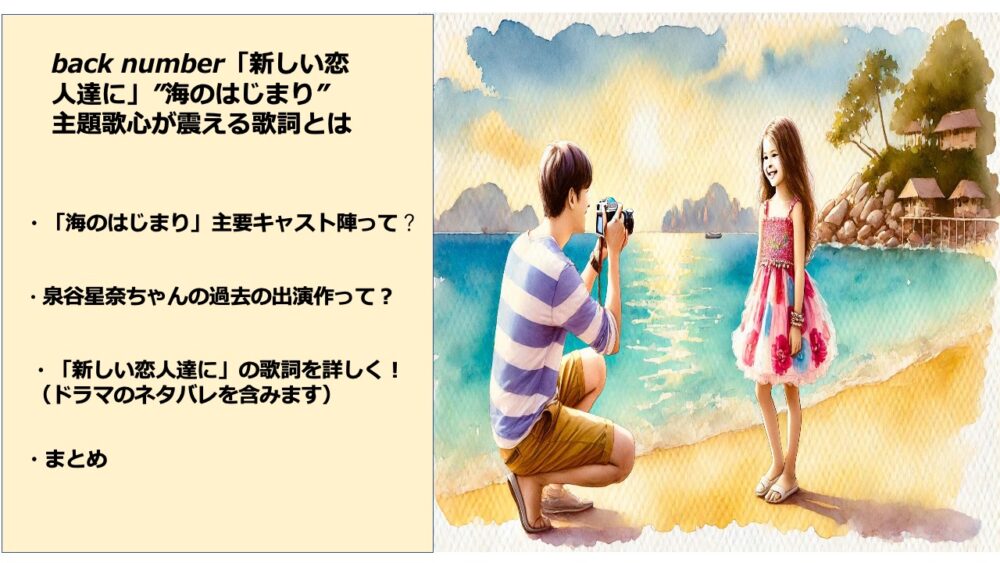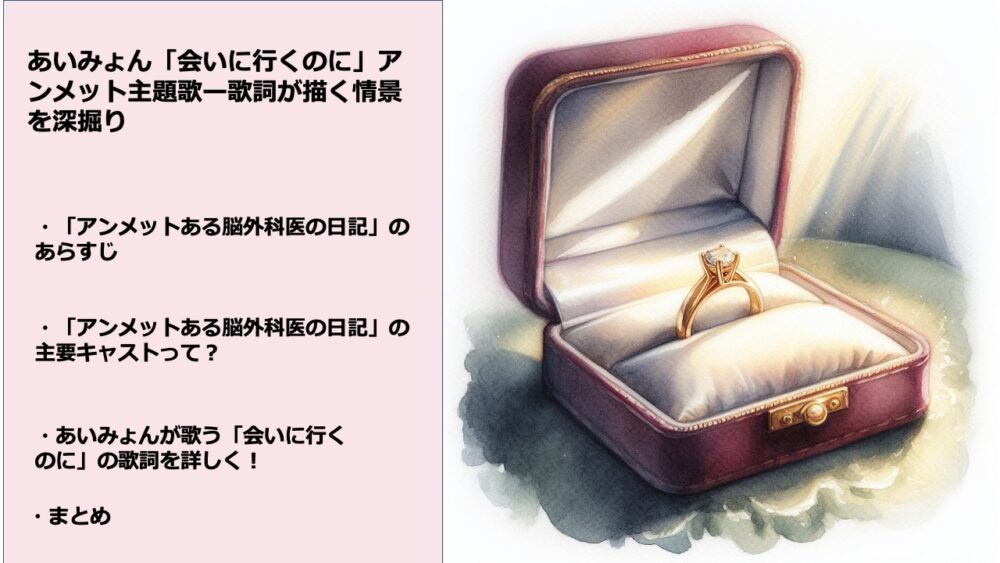こんにちは。キノコって季節的に秋冬のイメージですが、1年中店頭に並んでいるお馴染みの食材です。
キノコは見た目がかわいくて、色や形も様々です。キノコは食べるとおいしいし、健康にも良いと言われています。でも、キノコにはそれだけではない魅力があります。実は、キノコは自然界の不思議な生き物で、私たちが知らない驚きの能力を持っているのです。
このブログでは、キノコについて深く掘り下げてみたいと思います。キノコの歴史や分類、生態や生理、そして人間との関係について調べてみました。キノコに興味がある方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。キノコの不思議な世界に引き込まれるかもしれません。どうぞお楽しみに!
キノコの歴史とは?
キノコは地球上にどれくらい存在しているのでしょうか?
実は、キノコの祖先菌類は非常に古い生物で、約10億年前(約12億年前という説もあります)から地球上に存在しています。最初のキノコ(菌類)は水中で生活していましたが、約4億年前に陸上に進出しました。その後、植物や動物と共進化して、多様な種類が誕生しました。
キノコの起源は、原始的な真核生物である原生菌類から派生したと考えられています。原生菌類は水中で単細胞の鞭毛虫として遊泳したり、糸状体を形成したりしていました。その中から、糸状体を発達させて基質を分解する能力を持ったものが現代の菌類の祖先となりました。
少し専門用語が多くて難しいですよね。
原生菌類のイメージ図をご紹介しますね。

菌類、キノコの祖先はこんな感じかなと想像しています。
約10億年前の海の中には、こんな菌がたくさんいたのかもしれないですね。
鞭毛虫(べんもうちゅう)ってどんな虫ですか?
鞭毛虫(べんもうちゅう)(=flagellate)は、原生動物の中で鞭毛で運動する生物を総称する呼び方です。
鞭毛は細胞の一部が伸びた細長い構造で、水をかくことで推進力を得ます。鞭毛虫は約14万種類も存在すると推定されており、色や形、生態などは非常に多様です。鞭毛虫は分類学的には自然分類群ではなく、鞭毛を持つ原生生物の便宜的なまとめ方です。鞭毛虫の中には、葉緑体を持って光合成をするものや、バクテリアなどを捕食するものや、寄生性や病原性のものなどがあります。
鞭毛虫は単細胞生物ですが、群体を形成するものや、多細胞生物に近い特徴を持つものもあります。鞭毛虫は我々動物に最も近い単細胞生物であり、襟鞭毛虫というグループは動物の祖先と考えられています。
動物の祖先と言われている襟鞭毛虫もイメージが掴めないので、調べてみました。
襟鞭毛虫(えりべんもうちゅう)(=choanoflagellate)は、小さくて鞭毛を持つ原生生物の一群です。鞭毛の根元には、微細な突起が輪状に並んでおり、これを襟と呼びます。襟鞭毛虫は、襟と鞭毛を使って水中のバクテリアなどを捕食します。襟鞭毛虫は、単細胞生物の中では私たち動物に最も近い生き物であり、海綿動物の細胞と似ています。襟鞭毛虫は、単細胞のまま遊泳するものや、群体を形成するものや、殻を持つものなど、多様な形態を示します。襟鞭毛虫は、淡水域や海水域に広く分布していますが、目に見えないほど小さいため、あまり知られていません。
豆知識
10億年前に海の中で動物から分かれた菌類は、先ず「ツボカビ門」に進化し、その後、4億年前に原始的なカビの仲間である「アーバスキュラー菌根菌(菌と根の複合体)」が含まれる「接合菌門」に進化することで、鞭毛を喪失して陸上へ進出しました。
出典元:Kinokkusu Corporation公式サイトより
さて、いよいよ菌類が水中から陸上に進出します。
菌類は陸上へ進出する際に、植物や動物と共進化することで多様化しました。植物と共生することで光合成産物を得たり、動物に寄生することで栄養素を得たりする菌類が出現しました。また、植物や動物の遺骸を分解することで有機物循環に貢献する菌類も出現しました。
このようにして地球上にキノコが誕生していくんですね。本当に不思議です。
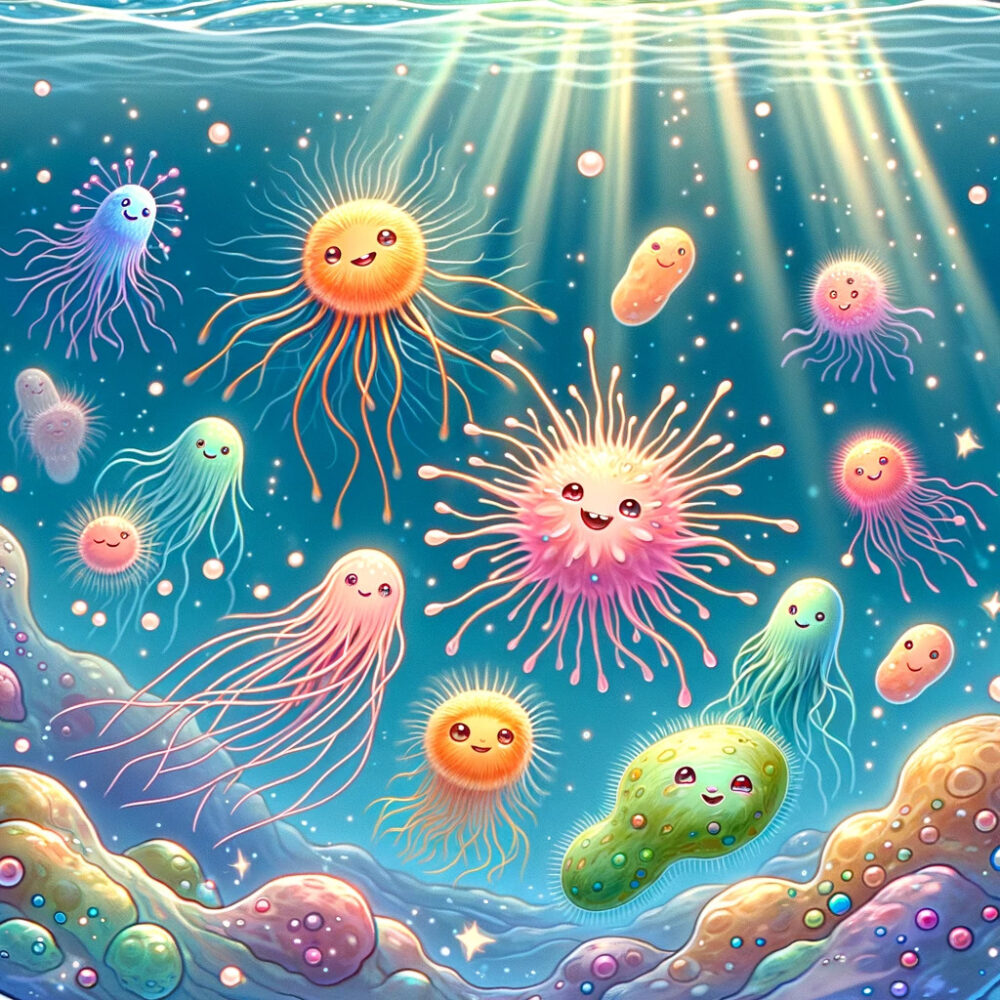
可愛い鞭毛虫たちです(笑)(きのこの祖先のイメージです
現在、地球上には約14万種類ものキノコが存在すると推定されています。しかし、そのうち発見されているのは約1万種類程度で、まだまだ未知のキノコがたくさんあると考えられます。また、キノコは分類学的には植物でも動物でもありません。独自の生物界「菌界」を形成しています。
キノコは地球上に約14万種類もあるそうですので、これからまだまだ新種のキノコが発見されるかもしれないですね。楽しみです
キノコの不思議な世界とは?
ところで、菌界は大きく分けて担子菌門(Basidiomycota)と子嚢菌門(Ascomycota)の二つの門に分かれます。担子菌門は傘やひだなどを持つ一般的なキノコやカビなどが属します。子嚢菌門はトリュフやカビロンなどが属します。これらの門以外にも接合菌門(Zygomycota)や卵菌門(Glomeromycota)などがありますが、キノコを形成するものは少ないです。
キノコは見た目だけではなく、内部構造や生活環も非常に不思議です。一般的に言われる「キノコ」という言葉は、実際には菌類が繁殖するために作り出す「子実体」と呼ばれる部分です。子実体からは胞子と呼ばれる微細な粒子が飛散し、新たな菌類を生み出します。
しかし、菌類の本体は子実体ではありません。菌類の本体は、細い糸状の細胞が集まってできた「菌糸体」と呼ばれるものです。菌糸体は土や木などの基質の中に広がり、栄養を吸収したり、分解したりします。
子実体と菌糸体って?
ちょっと、またまた難しいワードが出てきましたので、もう少しわかりやすく説明しますね。
キノコは、子実体と菌糸体という二つの部分に分けられます。子実体は、キノコの上の部分で、傘と柄からなります。私たちが普段食べたり見慣れているキノコは、子実体の部分です。子実体は、植物の実や花に相当する部分で、胞子を作る器官です。子実体は、栽培が難しく、成熟するまでに約4ヶ月かかります。
菌糸体は、キノコの下の部分で、根っこにあたります。菌糸体は、白い綿状の繊維で、土の中や木の中などに広がっています。菌糸体は、植物の根や種に相当する部分で、キノコの成長に必要な栄養を吸収したり、他の菌と交流したりします。菌糸体は、タンクで培養することができ、生産が容易です。
アガリクスというきのこは、子実体と菌糸体という二つの部分からなります。先ほど説明しましたように子実体とは、キノコの形まで育ったもので、傘と柄の部分です。菌糸体とは、キノコの根っこ部分で、白い綿状のものです。子実体は、繁殖に必要な胞子を作ります。菌糸体は、栄養を吸収したり、他の菌糸体と交配したりします。
子実体と菌糸体は、同じアガリクスの一部ですが、それぞれ違う成分を含んでいます。子実体には、β-(1-3)-D-グルカン、β-(1-6)-D-グルカン、キシログルカンなどの多糖類が多く含まれています。これらの多糖類は、免疫機能を高めたり、抗がん作用を示したりすると言われています。菌糸体には、グルコマンナンタンパク多糖体(ATOM)、マンナンタンパク質複合体(AB-FP)などの多糖タンパク質が多く含まれています。これらの多糖タンパク質は、血糖値や血圧を下げたり、腸内環境を改善したりすると言われています。
アガリクスの製品には、子実体と菌糸体のどちらか別々に使ったものがあります。子実体製品は、自然に育ったキノコを乾燥させたり、粉末にしたり、エキスにしたりしたものです。菌糸体製品は、タンクで培養した菌糸体を乾燥させたり、粉末にしたり、エキスにしたりしたものです。子実体製品は、自然の成分が豊富で、品質が高いとされています。菌糸体製品は、栽培が容易で、大量生産が可能です。しかし、菌糸体製品には、他の成分を混ぜたり、化学成分を使ったりする場合があるので、注意が必要です。
アガリクスは、子実体と菌糸体という二つの部分に分けられますが、それぞれに良い成分があります。アガリクスの製品を選ぶときは、自分の目的や体質に合わせて、子実体製品と菌糸体製品の違いを理解しておくと良いですね。
オニナラタケというきのこ
ところで、菌糸体は目に見えないほど小さいものから、数百メートルにも及ぶものまであります。世界最大の生物は、アメリカのオレゴン州にあるキノコの菌糸体は、面積は約8.9平方キロメートル、重さは約400トンと推定されています。このキノコはオニナラタケと呼ばれ、世界最大の生物とも考えられています。このキノコは木の根に寄生して栄養を吸収し、菌糸を地下に広げて成長します。このキノコの子実体は食用ですが、味はあまり良くなく、調理に注意が必要です。
オニナラタケの子実体は、茹でたり、焼いたり、煮たりして食べることができますが、生で食べると胃腸の不調を起こすことがあります。また、オニナラタケは、他のキノコと間違えやすいので、採取するときは十分に注意した方が良さそうですね。

(アメリカのオレゴン州にあるキノコの菌糸体(オニナラタケ)のイメージです)
キノコは生活環と呼ばれる一連の過程を経て繁殖します。担子菌門の場合、子実体から飛散した胞子が発芽して単相菌糸(n)を作ります。単相菌糸は他の単相菌糸と融合して重相菌糸(n+n)となります。重相菌糸は基質から栄養を得て成長し、特定の条件下で再び子実体を作ります。子実体の中では核が融合して二倍体(2n)となり、減数分裂して単相の担子胞子(n)を作ります。このようにして一生涯を終えます。
キノコは自然界の不思議な生き物で、私たちが知らない驚きの能力を持っています。例えば、発光する能力や放射能を分解する能力や薬効を持つ能力などです。これらの能力はキノコが生存や繁殖に有利になるために進化したものです。キノコは人間にとっても大切な存在で、食用や薬用だけでなく、文化や科学にも貢献しています。
次の章で、詳しくみていきたいと思います。
きのこの驚きの能力とは?
キノコは自然界の不思議な生き物で、私たちが知らない驚きの能力を持っています。例えば、以下のような能力です。
キノコには発光する種類があります。これは「生物発光」と呼ばれる現象で、キノコが酵素や化合物を使って光を発することです。発光するキノコは世界中に約80種類存在し、日本では「ショウゲンジ」と呼ばれるキノコが有名です。発光する理由はまだ完全に解明されていませんが、虫などの動物を引き寄せて胞子を運ばせるためだと考えられています。
キノコには放射能を分解する種類があります。これは「放射線菌」と呼ばれる現象で、キノコが放射性物質を無害化することです。放射線菌は世界中に約600種類存在し、日本では「ヒラタケ」と呼ばれるキノコが有名です。放射線菌はチェルノブイリや福島第一原子力発電所などの事故現場で発見されており、環境浄化に役立つ可能性があります。
キノコには薬効を持つ種類があります。これは「薬用菌」と呼ばれる現象で、キノコが有効成分を含んでいることです。薬用菌は世界中に約2000種類存在し、日本では「マイタケ」や「レイシ」などが有名です。薬用菌は免疫力や血圧、血糖値などに影響を与えることが報告されており、健康や美容に役立つ可能性があ流と言われています。
きのこと人間の関係とは?
キノコの歴史から始まり、様々キノコについてみてきましたが、キノコと私たち人間との関係も気になりますよね。
少し調べてみましたのでご覧くださいね。
芸術との関係
キノコは芸術家たちにもインスピレーションを与えてきました。キノコは色や形が多彩で、美しくも奇妙でもあります。キノコは絵画や彫刻、写真やイラストなどの様々な表現形式で描かれてきました。
きのこの絵を描いた画家は、何人かいらっしゃいます。その中で、特に有名なのは、小林路子さんです。
小林路子さんは、野生のキノコを描く「菌類画」の第一人者で、これまでに約900点の作品を発表しています。彼女の作品は、きのこの形や色、質感を細かく再現した写実的なもので、植物や菌類図譜の世界的コレクションを誇るイギリス・キュー王立植物園に収蔵されています。彼女の代表作には、「きのこの迷宮」や「きのこの絵本」などがあります。
小林路子さんの作品の画像は、以下のサイトで見ることができますよ。

神秘的な儀式との関係
キノコの中には幻覚作用を持つ種類があります。これは「幻覚菌」と呼ばれる現象で、キノコが神経伝達物質に影響を与えて、視覚や聴覚などに異常な感覚をもたらすことです。
幻覚菌は世界中に約200種類存在し、マジックマッシュルームと呼ばれる「ヒカゲシビレタケ」などが有名です。幻覚菌は古代から宗教的な儀式や神秘的な体験に使われてきました。
例えば植物が宗教的なものに利用されたという神話はいくつかあります。キノコとは関係ないかもしれませんが、植物がインドや中国では「ソーマ」と呼ばれる神聖な飲み物に使われたそうです。その原料が何かの植物片だと言われていますが、確かなことはまだわかっていません。また、メキシコや南米では「テオナナカトル」と呼ばれる神のキノコに使われたと考えられています。このキノコを神聖なものとしての扱っているのは原住民の間に現代まで続いているそうです。(幻覚菌があるので怖いですね)」

食べると危険なので、絶対に間違って食べないでくださいね。
インドのソーマという飲み物は、古代インドの神話や祭祀に関係する興奮性の飲料です。ソーマは、特殊な植物の液汁を発酵させて作られたと考えられていますが、その植物の正体は不明です。ソーマは、神々や人間に不老不死や霊感をもたらすとされ、神酒として神聖視されていました。ソーマは、ヴェーダの祭祀で用いられる一種の供物であり、リグ・ヴェーダの第9巻はすべてソーマに捧げられた賛歌で構成されています。ソーマは、後に月の神と同一視されたり、シヴァ神の別名となったりするなど、多彩な神話を生み出しました。ソーマは、インドだけでなく、イランのゾロアスター教にも同じような飲料(ハオマ)として存在しており、インド・イラン時代にさかのぼる古い起源を持っていると考えられています。
ところで、ソーマといえば、漫画の「食戟のソーマ」が有名ですね。インドの飲み物より、こちらの漫画を思い浮かべた方の方が多いような気がします
「食戟のソーマ」は、料理をテーマにしたバトル漫画で、下町の定食屋を営む中学生・幸平創真が、父親の勧めで超エリートの料理学校に入学し、食戟と呼ばれる料理対決に挑んでいく物語です。ソーマとは、創真の名前のほかに、古代インドの神話や祭祀に関係する興奮性の飲料の名前でもあります。この作品は、附田祐斗さんが原作、佐伯俊さんが漫画、森崎友紀さんがキャラクター原案を担当しています。『週刊少年ジャンプ』に2012年から2019年まで連載され、アニメ化や実写映画化もされました。
科学との関係
キノコは科学者たちにも興味深い研究対象となってきました。キノコは生物学や化学、医学や農学などの様々な分野で研究されてきました。キノコは生命の起源や進化、生態系や環境問題、病気や薬物などに関わる重要な役割を果たしています。
きのこに関係する研究とは?
①きのこは、枯れ木や落ち葉などの有機物を分解する腐生菌と、生きた植物の根と共生する菌根菌に分けられます。腐生菌は、森林の循環システムにおいて重要な役割を果たし、リグニンなどの難分解性の物質も分解できます。菌根菌は、植物の水や無機養分の吸収を助け、細根部の抵抗性を高めます。これらのきのこの生育に関する研究は、森林総合研究所などで行われています。
森林総合研究所の公式サイトはこちら↓
②きのこは、食用や健康食品としてだけでなく、生体機能調節効果や医薬品の原料としても注目されています。例えば、シイタケに含まれるレンチナンは、免疫力を高める効果があるとされ、がん治療の補助薬として使われています。また、ヒイロチャワンダケに含まれるエリンギンは、血圧を下げる効果があるとされ、高血圧の予防に役立つと考えられています。きのこの成分や栄養に関する研究は、日本特用林産振興会などで行われています。
日本特用林産振興会の公式サイトはこちら↓
③きのこは、落雷によって収穫量が増加するという伝承がありますが、これには科学的な根拠があることが実験で分かっています。落雷によって、きのこの胞子が活性化したり、菌糸が刺激されたりすることで、きのこの発生が促進されると考えられています。落雷ときのこの関係に関する研究は、ナショナル ジオグラフィックなどで紹介されています。
ナショナル ジオグラフィックの公式サイトはこちら↓
落雷とキノコの関係の記事はこちら↓

まとめ
今回、「キノコの不思議な世界:見た目だけじゃないキノコの驚きの能力」という内容で、ブログ記事をまとめてみました。いかがでしたでしょうか?
キノコは、私たちの目に見える部分だけではなく、地中に広がる菌糸体というネットワークを持っています。この菌糸体は、他の植物や動物とのコミュニケーションや協力に役立ちます。例えば、キノコは木と共生して栄養を交換したり、森の中で情報を伝達したり、環境に適応したりすることができます 。また、キノコは、抗生物質や発光物質などの特殊な化合物を生成する能力も持っています 。これらの化合物は、キノコの防御や生存に役立つだけでなく、人間の様々な分野に利用されていることがわかりました。
キノコのことを調べていくと、キノコは見た目だけではなく、その能力や役割にも驚きや発見がたくさんありました。キノコは、自然界の中で重要な役割を果たしており、私たちの生活にも多大な影響を与えています。キノコの不思議な世界が、少しでもご参考になれば嬉しいです。
最後までご覧いただきましてありがとうございました!
※様々なデータを参考にして執筆しましたが、きのこに関するデータは新たな発見があったり、年月とともに変わったりする場合がありますので、どうぞご了承ください。(このブログの内容は2023年11月時点でのデータに基づいています)